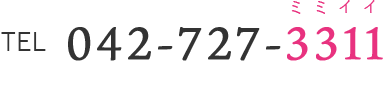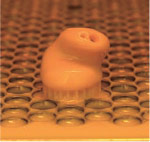補聴器を使ったことがない方、そのご家族の方へ
最近「聞こえにくいな?」と感じ始めた方、ご家族の聞こえが心配な方、普段の生活で少し聞き取りにくいだけだから、まだ大丈夫だろうと思っていても、耳が遠くなると不便なだけでなく、事故に結びついたりと危険が増えます。
また、装用したご本人だけでなく、ご家族や周りの方にも影響があるものです。
つけてよかったとお声をいただく方は、装用されたご本人だけでなく、そのご家族・周りの方からの声もとても多いのです。
周りの方のためにも、ご自身の聞こえの状態がどの程度のものなのか、補聴器が必要なのか、聞こえの専門家にご相談ください。
また、補聴器は購入後の調整などのアフターケアがとても重要です。
アフターケアがきちんと出来るお店で購入されることをお勧めします。
東京都町田市、町田駅近くになる「リオネット補聴器」取扱い補聴器専門店です。聞こえや補聴器に関することはお気軽にお問い合わせください。
リオネットセンター町田